【対談】LLMO診断160社で見えた“AIに選ばれる”LLMO実戦知

AI検索時代に選ばれるブランドへ。未来の顧客接点を作る、LLM最適化。
LANYがLLMOコンサルティングの提供をはじめて数か月。代表 竹内を含むマネジメントが現場にフルコミットし、今や160社*を超える企業にLLMO診断を提供してきました。
「とにかくまずは量。スマートに泥臭く、誰よりも深くこの領域を掘り下げる」
この「量×検証をやり切る」姿勢で、AI検索時代のマーケティング戦略において圧倒的な知見を蓄積し、出た結論はシンプル。
LLMOは“めっちゃマーケ”。
強みを言葉にし、外に出し、AIと人の両方に取りやすい形で更新し続けることが、“AIに選ばれる”近道でした。
本対談では、竹内・原・林・永江が戦略レイヤーの気づきと現場でゴリゴリ手を動かして掴んだ手触りを語ります。
*160社:2025年10月社内集計値
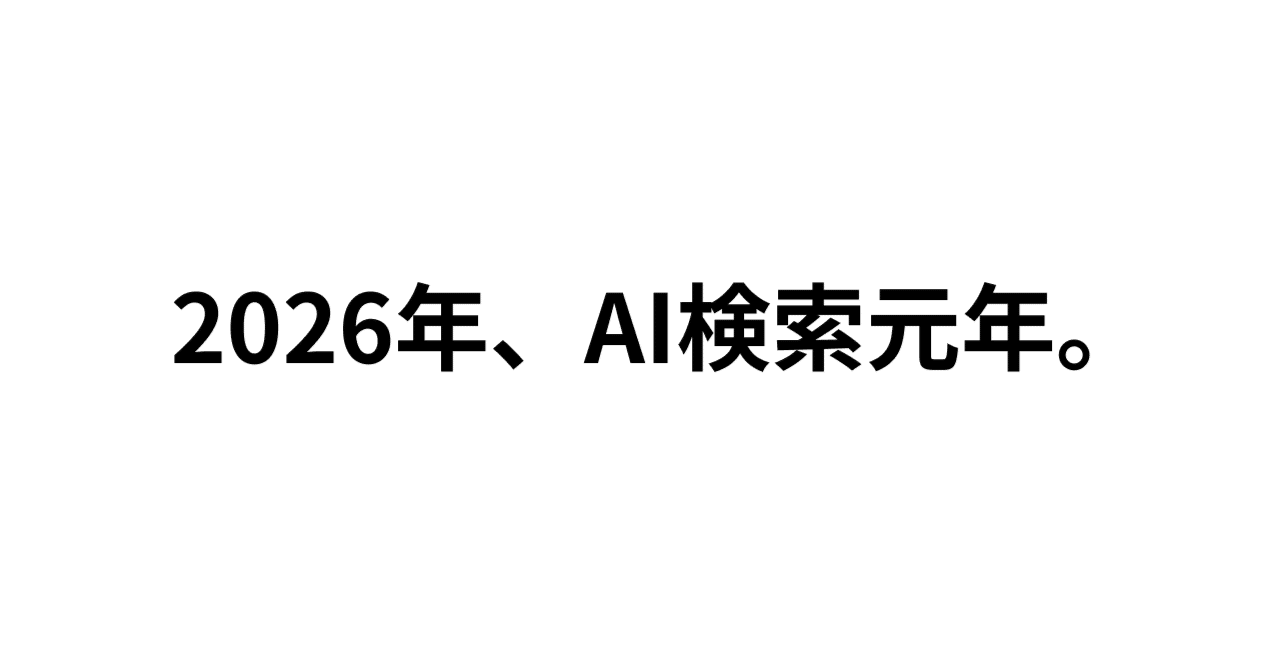
【竹内 渓太/株式会社LANY 代表】
・新卒で株式会社リクルートホールディングスに入社し、3年間SEOや広告運用、BtoBマーケなど幅広いデジタルマーケティング業務に従事
・X(@take_404)やYouTubeで「SEOおたく」として情報発信を行う
・著書に『強いSEO』『強いBtoBマーケティング』『強いLLMO』(エムディエヌコーポレーション)
▶︎竹内のインタビュー
【原 千洋/マーケティング・セールス チームリーダー】
・営業職としては、求人広告代理店でキャリアをスタート
・資格情報のBtoCメディア運営会社で営業職とマーケティング職を兼務
・転職後、学習管理システム(LMS)提供会社にてインハウスマーケターになる
・LANYでは、営業とマーケティングの経験を活かしてセールスを担当
・休日は音楽を聴いたり、カレーを食べに行ったりして過ごすのが好き
▶︎原の社員インタビュー
【林 佑樹/グループマネージャー】
・大学卒業後、上場企業にてBtoBマーケティング全般を経験する
・転職してSEOメディアの立ち上げ〜グロース、クリニックマーケティングなど、デジタルマーケティングのノウハウを学ぶ
・LANYにてメディアサービス型のコンサルティングチームのマネージャーを務めている
・趣味はサウナ・旅行・スポーツ観戦・漫画など
▶︎林の社員インタビュー
【永江 竜佑/グループマネージャー】
・新卒で広告代理店に入社後、複数の事業会社でSEO・広告・CRMなど幅広いマーケティングを担当
・SEOチームの立ち上げやモニタリング体制の構築、CRMを活用したユーザー接点の強化にも従事
・現在はSEOコンサルタントとして、事業会社での実務経験をもとに課題解決を支援中
LLMO診断160社やってわかったこと
 LANY代表 竹内
LANY代表 竹内
SEOからマーケティング総論へ
竹内:この数か月、全社でLLMOに取り組んできて、気がつけばLLMO診断を実施した数は160社まで到達しました。チームリーダーやマネージャーレイヤー、そして僕自身もがっつり現場に入って手を動かしてきた中で見えたことを整理したくて、集まってもらいました!
これまでの手応えは、どうでしたか?
永江:率直に、忙しいけれど楽しい時間でした!変化でいうと、従来のSEOは「各論」(タイトルや内部リンクなど個別施策)への比重が大きかったのに対して、いまのLLM文脈では「全体論」──事業・サービスの強みの言語化や業界でのポジショニングの明確化の重要度が上がっています。強みを特定しないと各論が始められない、という感覚に変わりました。
 LANY 永江
LANY 永江
林:同意です。検索のタッチポイントは、もうSEOやリスティング広告といったGoogleのSERPs(検索結果画面)だけでは完結しにくい局面が増え、SNS、レビュー・比較サイト、そしてLLMの回答などに広がっている。だからこそ、全方位で同じメッセージを一貫して届ける設計が必要です。いわば「検索マーケティングの統括」としての横断視点が求められている、と。
竹内:まさに!僕たちの仕事は、SEOという局所対策から、事業全体を捉えるマーケティング総論へと重心が移った実感があります。市場がどう変わっているか→だから今、こう設計するという語り口にアップデートされた。
林:これまではSEOの専門家としてお客様と関わることが多かったのですが、いまは「マーケティングコンサルタント」としてプロダクトやプロモーションといったマーケティングの4Pから逆算し、最適な手段の組み合わせを設計する役割へとシフトしています。
 LANY 林
LANY 林
竹内:いいですね!その姿勢は、林さんがCULTUREで語っていた「手段から入らず、目的から考える。最短距離の手段を柔軟に選ぶ」というスタンスそのもの。LLMOでも、手段に縛られず“問い”から入る動き方を体現してくれていると思います。
本質はそのまま。“伝え切る”をAI目線に
原:みなさんがおっしゃるとおり、視座はマーケティング戦略にぐっと寄りました。ただ、LLMOだからといってまったく新しい魔法が必要になったわけではありません。やることは昔から同じで、「ユーザーに自社を選んでもらうために、何をどう伝え切るか」──その本質をAIにもわかる形で設計し直すだけです。
竹内:うんうん。そのとおりですね。
原:LLMの役割は、ユーザーの問いに最適な回答を返すこと。だからこちらは、LLMが根拠として評価しやすい事例や数字、第三者からの言及をきちんと用意して、AIを介してユーザーに届ける。AIが見る根拠は、人が比較時に重視する情報とズレにくいと感じています。
 LANY 原
LANY 原
竹内:まさに!人もAIも重視する根拠は同じ。僕たちがLLMO診断でやっているのは、お客様の強みを客観的に棚卸し、「これって実はめっちゃ強みですよ」と可視化し、PESO(Paid/Earned/Shared/Owned)を横断しながら、AIが評価しやすい定量的な数字やファクトベースの情報としてWeb空間に落とし込む作業。
いわばコーチング的に強みを引き出し、最短の伝わり方に設計する仕事です。これは、LANYのミッション「価値あるモノをインデックスさせる」の伏線回収になっている実感があって、めっちゃうれしくって。あ、熱くなって語りすぎてきた(笑)

一同:(笑)
永江:今スイッチ入りましたね笑
原:ミッションの伏線回収、めっちゃかっこいいです!
10年先から今を決め「経営ドリブン」で動く
竹内:ここからは市場側の変化も少し。最近の動向として、超トップダウンでLLMOに着手する企業が非常に増えてきています。
現場はどうしても「足元のKPI」で評価されがちですが、経営層は「10年後に会社はどうあるべきか」という視点で意思決定をする。AIにおけるパラダイムシフトを、「これはチャンスだ」と捉える空気感と「今のうちに手を打つ」という健全な危機感が同居しているように感じます。
林:いまは立ち上げ期ゆえ、短期指標だけでは測りにくい。まさに黎明期ならではですね。
竹内:だからこそ、僕たちの提案の語り口もアップデートしました。以前までは「ここがネックなので直しましょう」というAs-Is/To-Beの「改善型」が中心でしたが、今は「マーケットがこう変わる→だからこれをやっていきましょう」という「戦略型」の対話がベースです。
永江:“To-Be(目指す姿)”の位置をより高くしたことで、僕たち自身の視座もめっちゃ上がりましたよね。

惚れ込むほど解像度が上がる
竹内:以前CULTUREの対談で「友だち作りたいから支援会社やってる」という話をさせてもらったんですが、LLMO診断をしていると好きな会社やサービス・プロダクトが無限に増えてくる!
原:わかります!無料診断では初対面のお客様とお話することが多いのですが、お相手の方に「LANYさんは、なぜこんなに弊社のサービス好きになってくれているんだろう?」みたいな顔をされることがあります(笑)
でも、素敵なところを見つけると、「ここをAIに認識させないと、めちゃくちゃもったいない!」って本気で思うんです。この熱量が、ご支援の原動力になっている気がしますね。

竹内:間違いないですね!AIに選ばれる設計は、プロダクトを好きでないと進まない。好きになるほど言葉が磨かれ、PESOをまたいで同じメッセージに落とし込める。誰に、何が、どう効くのか──強みの芯を僕たち自身が理解しているかどうかが、最後の差になる。
永江:うんうん。そうですね。まずは会社の強みや価値を一緒に見つけさせてもらったり深めさせてもらって、その情報をちゃんと表に出す。人が選びやすいように、かつAIが理解できるフォーマットで。LLMOにはそれが必要で、伴走させていただく我々も同じ目線と熱量で取り組んでいきたいですね。
LLMOの“難易度が上がりやすい局面”

差分が外から見えにくい場では根拠が拾われにくい
竹内:苦労したことで言うと、コモディティ化しているプロダクトや、ポータルサイトなどの中間媒体は、LLMOの難易度が上がりやすい。
原:同意です。掲載情報がほぼ同じだと、AIが候補として挙げる根拠が外から見つけにくくなってしまって…。
林:あと、構造面ではプロダクトのサービスサイトのサブディレクトリなどにある「コンセプトが切り離されたオウンドメディア」は、LLMOを推進しにくく、扱いがとても難しいですね。
“短期KPIに乗りにくい価値”をどう扱うか

永江:LLMOは各論よりも“全体の位置づけ”が先です。市場での立ち位置と強みを定めないと、その後の施策が意味を持ちにくい。具体と抽象の往復が難所だと感じます。
林:それもありますね。SEOとのリターン比較の観点でも、SEOのほうが費用対効果が明確に出る局面はまだあります。だから、メディアに対してLLMOにも注力すべきと主張するには、根拠や事例の蓄積が必要で、説明が難しい場面も…。
竹内:うんうん。あと、成果の見え方も難点だと思っていて。たとえばLLMで比較→指名検索で来訪という流れだと、現行の計測仕様ではセッションが分断され、AI推奨率の上昇が事業インパクトにどう効いたかを厳密に説明しにくい。
原:営業の現場では、プロダクトが“キャズム越え”前という事情もあり、単体の施策としての導入を判断いただくのが難しいケースがあります。セッションやCVが何%上がるかを即答しづらいので、お客様も“やるべき”とわかっていても予算化に踏み切れないことがあるんです。
だからこそ、ブランドやプロダクトの将来像を見ているレイヤーの方とお話できるとよりスムーズに進みやすい、というのが正直な実感ですね。

代表もMgrもプレイヤー──“スマートに泥臭く”が質と速度を上げる
竹内:LLMOという未開の地を切り拓くには、誰よりも深く潜り、誰よりも早く発見し続ける必要があります。
だからこそ、LANYらしく専門性にこだわるご支援ができている実感がありますが、みんなはどう感じていますか?
“精神と時の部屋”で得た経験値
原:セールスの立場からですと、竹内さんやマネージャー陣が前線にいることで、本当に多くのお客様と向き合える機会が生まれました。特にLLMOの無料診断という「発明」があったことで、短期間で膨大なケーススタディを得られました。通常ならもっと時間をかけて貯まる経験値が、“精神と時の部屋”のようにギュッと凝縮された感覚です!

一同:「精神と時の部屋」(笑)
竹内:黎明期だからこそ、全員で楽しんで研究を重ねられている。会社としてもLLMOの理解度が上がり、トップランナーを走れている実感があります。
何より誇らしいのは、みんなの“ディグる”(掘る)姿勢。「こんな発見がありました!」とワクワクしながら共有してくれる。この好奇心の連鎖が、LANYらしくて良い!

永江:ディグれて楽しいです!
現場発の専門性と熱量が伝播する
永江:あと、マネージャー自身が手を動かすので、そこで得た知見のフィードバックが速い。いわゆる「管理が上手い」ではなく、一番マネージャーが詳しくて、その知見をみんなに伝えていくという体制が回っている感覚です。「一番やっている人の言葉」だから、メンバーも納得して受け取ってくれているのかな、と。
林:同感です。サービスや仕様が日進月歩で変わるなか、現場を見ているからこそ「ここは任せる/ここは任せない」の線引きが早く、的確になります。その結果、自走できるメンバーが着実に増えている。
さらに、竹内さんが現場に入ると、品質と速度が同時に上がります。レビューの観点や評価軸がその場で言語化・更新されるので、迷いが減るんですよね。
永江:カルチャー醸成の面でも大きいですね。竹内さんがいちばんの発信者として社内外でLLMOを語り続けてくれるから、メンバーが迷わずそこ(LLMO)に向かっていける空気がある。
林:本当にそう思います!竹内さんが毎日のように新しい気づきを社内に持ち込んでくださるので、メンバーの没入度が上がります。社内のスレッドや定例で共有される内容が、僕たちにとっては“最新の教科書”みたいな存在。結果として、会社全体の基準がそろうんですよね。

永江:この記事を読んでくださる方にも、自然と熱量の高さを感じていただけると思いますね。
竹内:うれしい!これからも呼吸のようにSlackに投稿していきます(笑)
仮説を確信に、知見を組織へ
竹内:僕たちは現場で泥臭く試行錯誤しつつ、LLMの技術に明るい外部の専門家にも壁打ち(技術検証)をお願いしています。
現場で「たぶんこうだ」という仮説が生まれたとき、その方に技術的な裏付けをしてもらう。「LLMの学習はこういう風に行われているから、それは違う。こうだと思うよ」と、仮説を「確信」に変えてもらうことで、前に進めていますよね。
永江:そうですね。僕たちが泥臭く殴り書きで見つけた仮説が、専門家とのミーティングで「答え合わせ」というか、言語化・体系化される。あの瞬間が個人的には一番好きで、具体と抽象を行き来する感じが、この仕事のおもしろさだと感じています。

竹内:ですよね!あの瞬間すごく楽しい!そうやって磨いた知見は、シンクタンク的に発信もしています。「LANY LLMO LAB」では、分析結果・調査レポート・専門家との対談などをまとめて公開し、社内外の共有資産にしていくつもりです。
「価値あるモノをインデックスさせる」ために──LANYの覚悟

竹内:LANYは「目に見えにくいものに投資して勝つ」を積み重ねてきました。思いつきではなく、この5年の僕たちなりの機械学習の積み上げから、「この方向に進めば良い未来をつくれる」という手応えがあるからです。
いまはAIが台頭し、LLMOがそのブレイクスルーの中核だと確信しています。だからこそ楽しんで専門性を磨き続け、お客様の事業を最短で前に進める会社でありたい。
意思決定の基準は、人もAIも大きくはズレません。むしろAIが広がるほど訴求だけに頼るやり方は効きにくくなり、実体の価値と事例・数字・第三者の声といったその根拠が評価されやすい──そんな傾向が強まっていると感じます。
僕たちはこれからも「価値あるモノをインデックスさせる」というミッションのもと、お客様のプロダクトやサービスを深く好きになって、必要とする人とAIの両方に届ける支援をやり切ります。
▼LANYのLLMOコンサルティングの強さの秘訣やコンサルタントとして働く上でのやりがいについて紹介しています
【カジュアル面談/ランチ】まずは気軽にLANYとお話してみませんか?
転職活動の有無に関係なく、LANYのメンバーとフラットにお話しませんか?
- 実際どんな人たちと働くの?
- どんな価値観を大事にしている会社なの?
- 自分の経験ってLANYで活かせる?
そんな素朴な疑問や不安を、ざっくばらんにお答えします!
話せるテーマの例
- LANYのカルチャーや働き方
- 現場メンバーの1日の仕事の流れ
- 成長機会、チャレンジできる領域
- あなたの興味や今後の方向性の相談
「まずは雰囲気を知りたい」「話しやすい人たちか確認したい」
そんな軽い気持ちで、ぜひご参加ください!
デジタルマーケティングのお悩み、
まずはお気軽にご相談ください。
サービス詳細は資料でもご確認いただけます。












