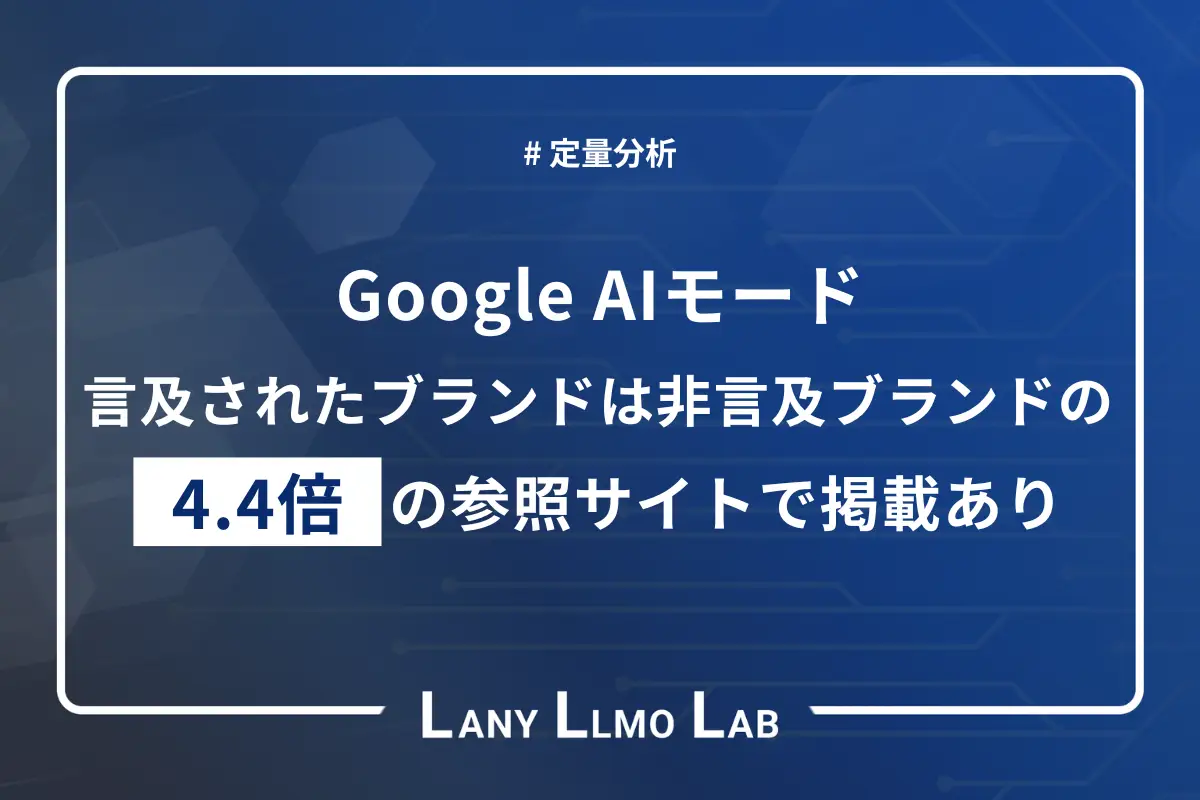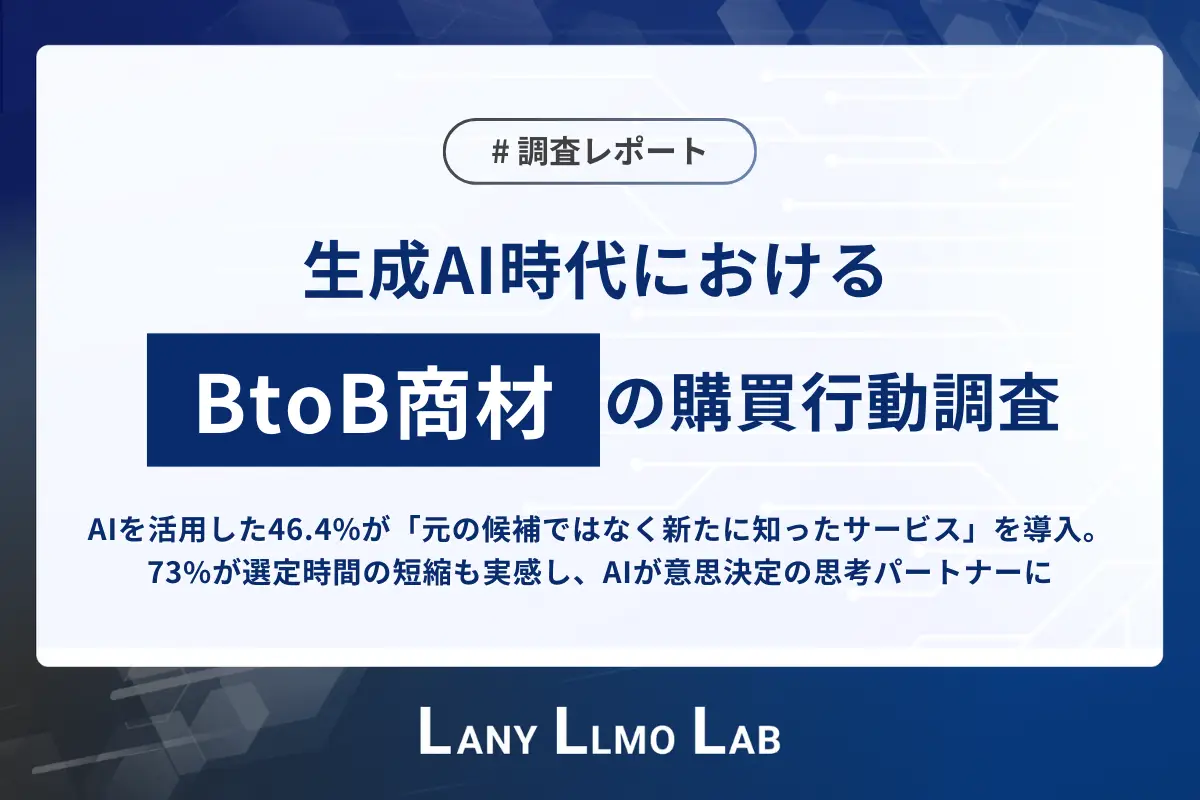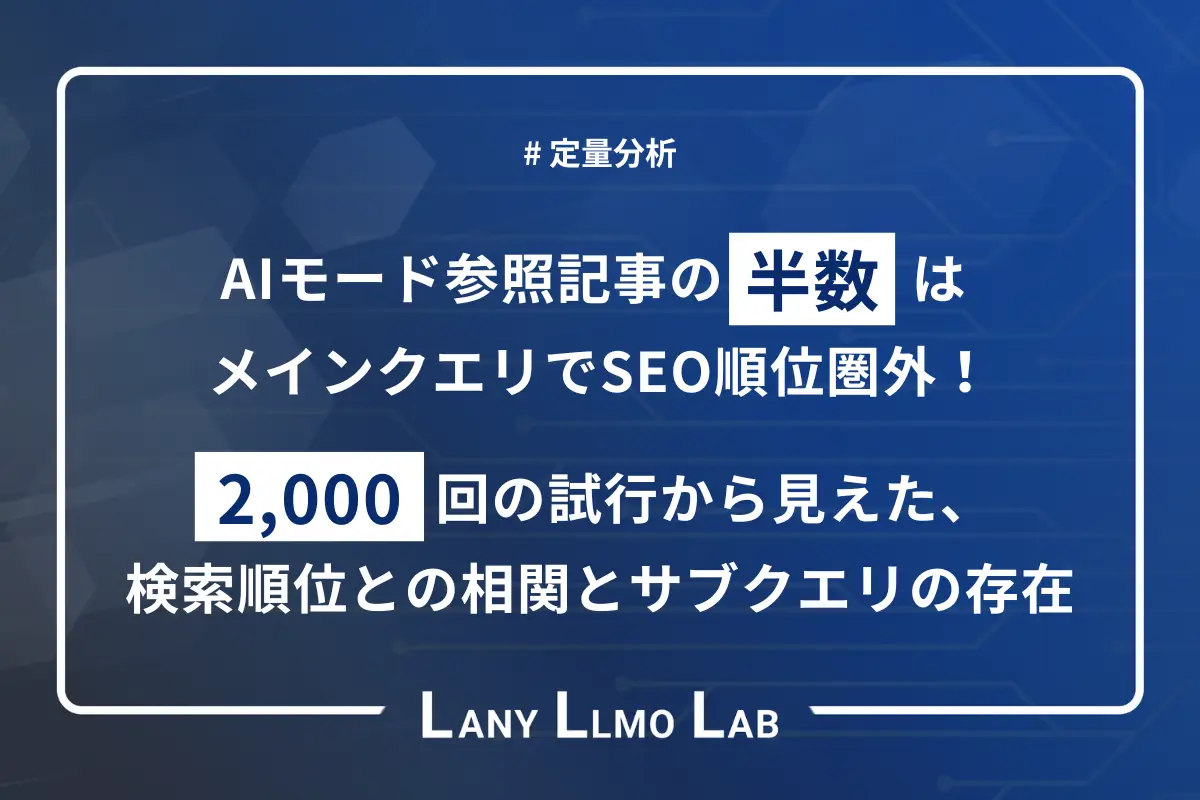AIが「ファクト」で選ぶ時代。ブランドマーケティングにLLMOが必要な理由 - 元リクルート・金井統氏と探る、「合理」で選ばれるブランドの未来

Google検索だけでなく、AIを利用した情報収集や比較検討を行う検索行動が少しずつ増えてきています。ユーザーがChatGPTやGeminiといった生成AIに相談し、その回答を参考に意思決定を行う場面も、今後さらに広がっていくでしょう。
そうした中で、AIが自社サービスをどう理解し、どのように紹介するのかはブランド戦略において無視できないテーマになりつつあります。
これまでのブランドは「イメージ」や「世界観」といった情緒的価値の訴求を得意としてきましたが、生成AIは膨大な情報を網羅的に読み取り、ユーザーニーズに最も適すると判断した選択肢を合理的に導き出す仕組みで動いています。
そのため、AIが回答を組み立てる過程で、ブランドを適切に理解し、選択肢として推薦してもらうための情報設計が、これまで以上に重要になるはずです。
言い換えると、ブランドマーケティングの中に 「AIにブランドを適切に伝達し、推薦される状態をつくる」ための取り組み――すなわち LLMO(大規模言語モデル最適化)が組み込まれる必要があるということです。
今回はリクルートのマーケティング室ヴァイスプレジデント時代に数百億円規模のブランド投資を手掛け、現在もマーケティングを起点に企業の成長支援に携わる株式会社NexGen CEOの金井統さんと対談しました。
ブランドとデジタルをどう掛け合わせ、AI時代のブランド戦略を再定義していくのか。そのヒントを探ります。
【金井 統/株式会社NexGen CEO、株式会社LANY 社外取締役】
株式会社リクルートのマーケティング室VP(ヴァイスプレジデント)として、会社横断の人材育成・知見流通とHR領域のマーケティングを管掌。 ToC/ToB双方のプロダクト横断での事業・マーケティング戦略、ブランドからdirectADやSEO、CRMに至るまでの統合マーケティング戦略による事業成長を牽引。事業戦略及びブランドを含めた統合マーケティング、組織・人材育成マネジメントが専門。
従来のブランド投資の考え方
竹内:
金井さんのキャリア的には、最初は獲得型のマーケティングから入って、その後ブランドなどの認知領域にも染み出されましたよね。僕が「認知領域のブランドマーケティングって難しいな」と思うのは、どうしても定量的な効果が測りにくい点です。
たとえばテレビCMを打って売上がどれくらい上がったのか、直接的にはわかりにくい。でも投資額は非常に大きい。いわゆる獲得に強いデジタルマーケティング出身の方がブランドマーケティングの世界に足を踏み入れるのって、文化の違いもあってすごく大変そうに思うんです。そのあたり、実際どうでしたか?
金井:
初めてブランドマーケティングを担当したときは、本当に苦労しました。
僕がリクルートで最初に担当したとある求人メディア事業は、リーマンショック直後の影響で、企業の採用意欲(需要)に対して求職者(供給)が非常に多い状況でした。そのため、広告宣伝費を使わなくても求職者からの応募が集まる状態で、しばらく広告予算がゼロになったんです。
しかし、景気が回復し始めると状況は一変。求人の掲載を希望する企業のニーズは増える一方、メディアのユーザーを集めるマーケティング組織がほぼなくなっていたのです。そこに、ただ一人配置されてマーケティング組織を立ち上げることになりました。当然デジタル分野に強い人材もいなかったので、自分で全てSEO、デジタル広告、アフィリエイト、アライアンス、全てのデジタルマーケティング施策をハンズオンで行っていました。ただ、それでも獲得系施策だけではクライアントが期待する応募数には到底追いつかず、すぐに限界がみえてしまいました。
そこで「トップラインを抜本的に引き上げるには『自社サービスの市場認知を一気に高め、市場全体の需要を呼び込む』しかない」と判断し、大規模なブランド投資に踏み切ったのがきっかけでした。
当時、ブランド投資への必要額を試算した結果「テレビCMに3億円投下すべきだ」という結論に至りました。ゼロからいきなり3億円の投資ですから、経営ボードからは当然「何を言っているんだ!」と大反発されました(笑)。
そこで証明したのが、純粋想起率とアクション数に明確な因果関係があることです。「CMによって純粋想起が高まれば、この指名検索数が伸びる。そして、指名検索の増加はこれだけの応募増加につながる」というデータに基づいたシミュレーションを何度も示し、最終的に投資の承認を得たのです。
竹内:
なるほど。当初はブランド投資をまったくしていない状態から、定量的なファクトを起点にブランド投資へと踏み込んでいったわけですね。
金井:
そうです。そこでの結果から「ブランドマーケティングはトップラインを大きく伸ばすために有効である」という確信を得て、ブランドとデジタルの両輪を回すスタイルを続けています。
竹内:
その延長で、BtoB向けの採用管理サービスのテレビCMも担当されましたよね。BtoBのCMって珍しいので、すごく大胆な決断だと思いました。
金井:
ブランド投資の考え方は、事業特性によって大きく異なります。
たとえばBtoBは市場が小さく、検索クエリの種類も非常に少ないという特徴があります。そこで、カギになるのがサービス名での「指名検索」です。
実際、市場で存在感のある企業はこの指名検索で非常に高いシェアを握っています。一方で、当時の僕たちはそこが明らかに弱かった。数字を見ても、「これは勝てる構造になっていないな」とすぐ分かるほどの差がありました。
つまり、獲得型のマーケティングだけを積み上げても勝てない構造だったんです。
だから、「選んでもらえる状態を最初からつくるしかない」という発想に切り替えました。
ブランド指名は、大量のブランドプロモーション投下をすれば一定あがります。ただし、やり方によって獲得効率には差が明確に出ます。ブランドネームからブランド訴求軸、プロモーション手法に至るまで細部にわたり設計がされていないといけない。
そこで私たちは、YouTube広告で検証した結果をもとにこれまでの覚えづらいブランド名を、想起効率の高い名称にリブランディングしました。
その際は広告データでブランドネームによる獲得効率に差があることを証明したのです。ブランドネームを変えると失うものもあるため、それ以上に得られる何かを証明する必要があったからです。
そのうえで、競合や他業界で大きくブランド指名数を伸ばしている会社の手法を改めて全て数字で分析して、勝ち筋を研究しました。すると、ROI観点では一見効率が悪くみえますが、年間を通じて継続的に投下し続けることでの勝ち筋がみえたのです。
ブランドプロモーションはできる限りLTVを伸ばして考えて投下の戦略を立てる必要があり、中途半端に行っても成果は得られません。そのことをデータで提示して100億円規模のブランド投資を行うという大きな決断をしました。
もちろん、これほどの大規模投資です。細かくモニタリングしながらチューニングは繰り返しました。その結果、ブランド指名の獲得効率を高く伸ばすことができて、競合を上回るアカウント数を実現することができました。
また、ToBは特に既存ユーザーが溜まっていくことで、新規ユーザーが増えていく構造にあります。つまり、ユーザー層の岩盤を一度創っていくと伸び続けていくことができるのです。
BtoB市場はターゲットが少ないからこそ、リーチできる確率は低くなります。だからこそ一度リーチしただけで獲得できるように施策を研磨する必要があることを学びました。
ブランドは情緒で選ばれる時代から、合理で選ばれる時代へ

竹内:
ブランドマーケティングの一つの役割が、何かを検討する際に脳内でまっ先に思い浮かぶ状態、いわゆる「第一想起」を獲得するためのものだと思っています。
そこで伺いたいのですが、2000年代から今に至るまで、このブランドマーケティングの役割は少しずつ変わってきているのでしょうか?特に今後のAI時代を見据えたときにどう変わるのかを聞いてみたいです。
金井:
そうですね。ブランドマーケティングでよく使われる言葉として「情緒的価値」と「機能的価値」の2つがあります。従来のテレビCMが力を持っていたのは、人の心に訴えかけて感情を動かすことができるからです。
つまり人は合理的に物事を選択しているわけではなく、感情によって意思決定している、という前提があった。だからこそ情緒に訴えかけるブランドマーケティングが成り立っていたんです。
ただ、AIが人々の意思決定に介在する時代になると、状況は変わります。AIは極めて合理的に選択する。つまり「情緒で選ばれていたブランド」から「合理で選ばれるブランド」へと変わっていかなければ、今後の時代では少し厳しくなるでしょう。
竹内:
以前は「このサービスなら、あそこだよね」という第一想起を獲得するため、各社がブランドイメージ向上に巨額の投資をしていました。まさしく、広告の投下量とクリエイティブで認知を競う「ブランド勝負」の世界でした。
しかし、その消耗戦から一歩抜け出し、近年は「ブランドイメージ広告」から「プロダクトの機能強化」へと戦略の舵を切る企業も出てきました。AIに、合理的かつ機能的に優れていることを明確に伝えることで推奨されるようにする戦略です。
「なんとなく知っているから」という非合理なブランド想起に頼るのではなく、AIエージェントがユーザーのニーズを汲み取り、「本当に自分に合ったサービス」を合理的に提案する世界。その時に「AIから選ばれる」ことで勝つ、という。
これこそブランドマーケティングの中に、AI検索最適化(AIエージェント最適化)の観点が含まれていくような戦略シフトだと思いますが、金井さんは、こうした動きは今後広がるとお考えですか?
金井:
間違いなく広がると思います。従来は検索によって情報収集と意思決定を同時に行っていましたが、AIはその情報収集を圧倒的な速さで代替してしまいます。となると、新しい選択肢への入り口はAI経由になりやすくなる。つまり、AIが合理的に候補をピックアップしてしまう時代に変わりつつあると思います。
なので、「合理的に選ぶAIに対して、どうやって選ばれる状態を作るか」を設計する段階に差し掛かっているのです。特に、高関与商材と呼ばれるような、価格や機能、契約条件などをユーザーがじっくり比較検討する領域では、この傾向が見られます。
生成AIが合理的に候補を提示する領域として非常に相性が良いこともあり、AI最適化へのシフトがすでに現れたんだと思います。
AI時代のブランドマーケティングは戦略PRとファクトベースの訴求が重要

竹内:
これまではCMなどを通じて商品の価値を伝え、ユーザーが「自分にはこれが必要だ」と気づくのを待つ、というアプローチも多かった。
でも、AIはもちろんCMを見ない。人がAIに相談するようになることを見据え、ちゃんとAIが理解できる形で、AIが選択で重視する「機能的価値」を伝えていく必要があると思っていて、その意味で「デジタル上での戦略的PR」が重要になるんじゃないかな、と。
機能的価値をAIに認識させ、それを必要とする人にマッチングさせる。これって、むしろ「本当に良いものが本当に必要な人に届く」という理想的な世界に近づくと思うんですが、金井さんはどう思いますか?
金井:
おっしゃる通りで、AI時代にデジタルPRが必要になるのは間違いありません。
PRの手法は、様々です。大きく大別すると、自社の強みを見出して社会に適合させていく方法と、強みを外から付与して社会に広めていく方法があると思います。
例えばサントリーのハイボールの事例は前者の良い事例です。当時、若者の間で「ビールは太る」という認識が広がりつつある中で、サントリーは「糖質が低い」「ヘルシー」というハイボールの機能的価値を見出しました。
それをメディアの力を使って発信した結果、若者に刺さり、ハイボールブームが起きました。
竹内:
確かに「糖質が低い」というのは分かりやすいファクトですね。
金井:
ファクト訴求による成功例として、女性向け下着メーカーのワコールもあります。
当時、ワコールはデザイン性を重視する競合ブランドの台頭により、特に若い女性からの支持に苦戦していました。この状況を打開する鍵となったのが、1964年から45年以上にわたり、延べ4万5千人もの女性の身体を計測・研究し続けてきた「ワコール人間科学研究所」の存在でした。
ワコールはまず、2010年にこの研究所が持つ膨大なデータから導き出した「加齢による体形変化の法則」を発表します。これは、「バストの下垂は20代から始まり、一度変化したら元には戻らない」「変化が少ない人は、自分のからだにあった着用感の下着を選んでいた」といった、科学的根拠に基づいた衝撃的な内容でした。
このファクトをニュースとして広く発信することで、多くのメディアが取り上げました。そして、「体型の変化について科学的な知見を持ち、正しいサイズを提案できる下着メーカーはどこか?」という問いの答えは、研究機関を唯一持っているワコールにたどり着きます。
これにより、ワコールは競合が得意としていた「デザイン」から、自社が圧倒的に強い「科学的根拠に基づいたジャストフィットな製品」で優位性を築くことに成功し、若い女性からの支持を再び集めることになりました。
これは単なる宣伝ではなく、ファクトを世の中に提示して「勝手に選ばれる」状態を作る、非常に巧みなメディアPRの戦略ですね。
僕は、AI時代におけるデジタルPRとは、このオンライン版だと考えています。
その時に重要になるのが「誰が」と「何を」という2つの要素です。「誰が」というのは、発信者に権威があるか、権威のあるドメインかということ。「何を」というのは、その中身がAIに合理的に選んでもらえるだけのファクトに基づいているかということです。
例えば掃除機で「ハウスダスト除去率99.9%」という強いファクトがあったとしても、多くの人は「本当だろうか?」と疑いますよね。AIはなおさらです。だからこそ、そのファクトを支える権威性とセットで、しっかりオンライン上に情報を載せていくことが、今後不可欠になると思います。
AI時代のブランド設計は潜在需要の掘り起こしがカギに

竹内:
プロダクトの強みを明確にして届けるアプローチと、市場の大きなニーズに合わせて寄せていくアプローチ。今後はこの両輪が必要だと思います。
LANYが取り組んでいるLLMOも、「ここは勝てる」というプロダクトやサービスの強みを見つけ、それがAIに学習されるようにオウンドメディアやペイドメディア、アーンドメディアを通じて情報を設計し、その強みを必要とする方々にAIを通して届けられる状態を作ろうと取り組んでいます。
金井:
素晴らしいと思います。ただその前提として、僕は必ず「市場規模を計算する」ことをやってきました。
AI時代に選ばれるブランド設計を考える時も同じで、強みをAIに学習させる前に、その強みを受け入れる人が何人いるのか、どのくらいの市場があるのかを定量的に押さえるのがカギになると思います。
僕がよくやるのはTAM(Total Addressable Market)からマーケットの規模を考えることです。SAM、SOMもありますが、TAMから構造的に考えないと、どの層を、どのぐらい動かせる余地があるのかを数字でシミュレーションできないからです。
今、顕在化している市場だけでなく、「潜在的に困っている人はどのくらいいるのか」を推計する方法なんですが、そこで役に立つのが国の統計情報です。あれは本当にすごい。
官僚が正確性を期して作っているので、ビジネス予測に十分使える。実際、統計を見れば次の市場構造が見えてくるんです。僕は必ず確認していました。
竹内:
それでいうとダイソンが日本国内でのシェアを広げたきっかけは「潜在的なニーズを掘り当てたから」という事例がありますよね。
金井:
まさしくそうです。
当時、「掃除機が欲しい」という顕在化した市場だけを見ていては、ダイソンのような高価格な製品が受け入れられる余地は小さく見えました。
しかし、視点を変えて「ハウスダストに悩んでいる」という潜在的な市場に目を向けると、統計上は日本に4000万人規模の巨大な市場が眠っていたのです。ダイソンはその市場の切り取り方に気づき、「ハウスダストをライトで可視化し、ウイルスを含む0.1ミクロンの粒子を99.9%除去」という機能訴求で勝負をしたと言えます。
したがって、ブランド設計も「潜在的に困っている人の母集団」を基点にするべきだと思います。インテリア需要として掃除機を買う人もいれば、健康課題として選ぶ人もいる。その切り口次第で市場規模がまったく変わります。
竹内:
確かに。AI時代になると、ユーザー自身も気づいていなかった潜在ニーズが喚起される場面が増えそうですよね。
AIは筋のいい質問を投げてくれるので、「ハウスダストで困っていませんか?」と問われれば、ユーザーが「確かに」と気づいて、結果的にダイソンをおすすめされる可能性がある。
そう考えると、顕在的なニーズ対応だけでなく、潜在ニーズに対応した機能価値をオンライン上にきちんと落としておくことが大事ですよね。でないと、合理的にAIが選択する場面で、選ばれない。
やはり「潜在需要に根を張ること」がこれからますます重要だと感じます。
AI時代のブランド投資は誰が旗を振り、いつ動くべきか?

竹内:
これまで人は「非合理的な選択」をしてきたからこそブランドに価値があったと思います。
ただ今後は、自分の悩みやこだわり、条件をAIに入力すれば「あなたに最適なのはこれです」と合理的な選択肢を推奨されるかもしれない。その方が自分に合ったサービスやプロダクトに出会える感覚もある。
そうなると、ブランド投資のあり方って少しずつ変わっていくんじゃないか、とも思うんです。この点についてどう考えますか?
金井:
まず、ブランドプロモーションへの投下金額自体は減少していくと思います。それは、リーチできるプラットフォームが数多く生まれて分散していっているからです。それに伴う形で投資の仕方が変わっていっています。
そもそもテレビの影響力が下がっていて、媒体がYouTubeなどデジタルにシフトしています。広告費全体は伸びていますが、オフラインからデジタルに移る構造の中で、単価が下がるのでブランド広告の投下額は相対的に減るはずです。
さらにYouTubeなどではCPMも低めなので、ブランド広告において動画系のプラットフォームに過剰に集中していた予算比率は、AIの登場により変わっていくとみています。人ではなく、AIが情報をピックアップする時代になっていくからです。
だからこそ常に「どこにどう投資するか」を考える必要があります。その判断をする人は、ブランド、デジタルといった意味のない境界線を超えてマーケティング全体を理解している人でないと難しいでしょう。
竹内:
実際、LLMOをご提案する際に、誰にアプローチすべきかは迷うところです。SEO担当なのか、ブランド担当なのか、マーケティング責任者なのか。
僕自身はSEOの延長として入るパターンと、もう少し上流の「検索や情報接点の全体設計」として入るパターンの両方で進めています。
ただ、今日のお話を伺うと、AI最適化に向けた推進はむしろブランド担当が考えるべきテーマのようにも思えてきました。
金井:
「誰が旗を振るべきか」という論点ですね。僕は2パターンあると思います。
ひとつは経営者。これは先行投資なので現場では決められず、経営が意思決定しないと始まらないからです。もうひとつはマーケティング責任者。ブランドもデジタルも両方を見ているような人。経営に「投資すべきだ」と提言できる視点を持たなければいけません。
この両者が動かないと組織として本格的に取り組めないと思います。
竹内:
なるほど。短期的な成果を追うというよりは、長い目で見た「資産づくり」に近い感覚で捉えていただくのが良さそうですね。
金井:
そうですね。生成AIの学習や信頼の獲得は、一朝一夕でできるものではありません。
だからこそ、今すぐに結果を求めるといよりは、「将来、自社ブランドがどう語られるべきか」という設計図を今のうちから描いておくことが大切だと思います。
焦る必要はありませんが、生成AIという新しいインフラが整いつつある今、少しずつでも「デジタル上に正しい情報を置く」という習慣をつけておくことで、結果として5年後、10年後のブランドの強さにつながっていくはずです。
竹内:
未来の顧客との接点を作るために、今から丁寧な情報を積み上げていく。それが次世代のブランド投資といえそうですね。
【サービス概要資料】LLMOコンサルティング
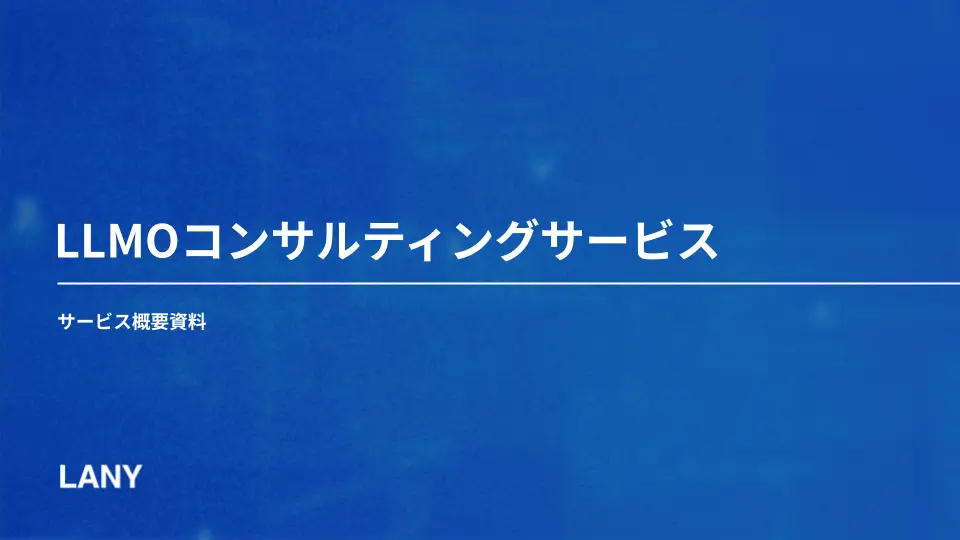
LANYのLLMOコンサルティングのサービス概要資料です。LANYのLLMOコンサルティングは、企業がAIにどう見られているかを可視化し、選ばれるブランドづくりを支援する包括的なサービスです。
デジタルマーケティングのお悩み、
まずはお気軽にご相談ください。
サービス詳細は資料でもご確認いただけます。